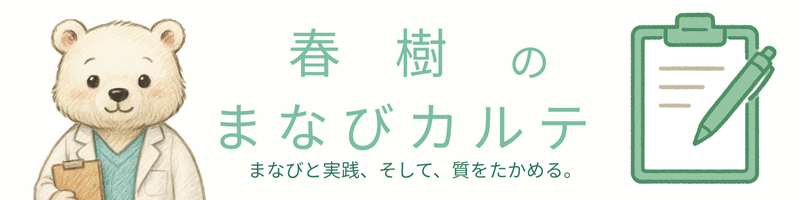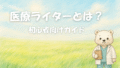子どもが「熱を出した」「息が苦しそう」と感じたとき、すぐに病院へ行くべきか、それとも少し様子を見るべきか——判断に迷った経験はありませんか?
焦っているときこそ冷静な判断が大切ですが、そのためには事前に正しい医療情報の調べ方を知っておくことが重要です。
この記事では、医療情報の探し方、信頼できる情報の見分け方、病院に行くかどうか迷ったときの判断基準をわかりやすく解説します。
信頼できる医療情報サイトもご紹介しますので、いざという時の備えとして、ぜひ最後までご覧ください。
今すぐ判断したい方へ ー 役立つリンク集
- こどもの救急(日本小児科学会)
症状にチェックを入れるだけで、受診の目安を教えてくれるサイトです。スマホ対応で見やすく、6歳までが対象ですが、それ以上の年齢でも参考になります。 - 小児救急電話相談#8000
小児科医や看護師から、直接アドバイスがもらえます。夜間や休日でも対応しており、迷ったときの心強い味方です。
医療情報はどうやって調べたらいいの?
スマートフォンを使って調べる
「夜中に子どもが発熱した」「苦しそうにして眠れない」そんなとき、多くの保護者の方はまずスマートフォンで症状について調べるのではないでしょうか。
けれど、検索して出てくる情報は玉石混淆。どれが正しい情報なのか判断に迷ってしまいますよね。ここでは、そんなときに少しでも信頼性の高い医療情報にたどり着くコツをご紹介します。
検索エンジンを選ぼう
医療情報を検索する際は、Googleを使うのがおすすめです。Googleは医療や健康などの分野において、信頼性の高い情報を上位に表示するように工夫されています。
公的機関や専門家が監修した情報にたどり着きやすくなるため、正確な情報を得るための近道になります。
いつ記載された情報かを確認しよう
医療情報は研究や開発により、より良い治療法などが日々変わっていきます。また、地域の救急体制なども変わっていることがあるので、記事を見るときにいつ記載された情報なのか、記事の更新などは行われているのかを確認しましょう。その記事だけではなく、Webサイト全体の更新頻度も確認しておくと、なお良いです。
知りたいことを明確にしよう
子どもの体調が悪そうなとき、「どんなことを知りたいのか」をはっきりさせると、調べる際のキーワードが的確になります。
たとえば:
- 発熱しているけど元気そう → 「子ども 熱 元気 病院 行くべき?」
- 咳が続いているが苦しそうではない → 「子ども 咳 何日続くと注意?」
信頼できる情報の見分け方
信頼できる情報の見分け方として、誰が書いたか、誰がチェックしているか、どんな機関が発信している情報かを確認することが重要です。
どこの誰が書いた情報かわからないものよりも、経験の豊富な専門家の記事の方が信頼が高く、安心できるのではないでしょうか。
公的機関が運営するサイト
厚生労働省、各都道府県保健局、都道府県単位の救急医療ガイドライン等。著者や監修者が明確で、地域の緊急対応などにも対応しているものが多く、非常に有益です。
病院が運営するサイト
特に公的病院や大学病院のWebサイトは、内容が充実しており、信頼できる情報が多く掲載されています。
民間企業が運営するサイト
企業が提供している情報は、その企業の関与する領域に特化している傾向があります。たとえば製薬会社なら、薬に関する情報が中心となります。
個人の体験談ブログなど
あくまで個人の感想として参考にとどめましょう。正確性や客観性に欠けることがあるため、判断の材料の一部として扱うのが安全です。
ドメインの確認
ドメインによって運営主体をある程度見分けることができます。
- .or.jp:医療法人・社団法人など
- .ac.jp:大学や教育機関
- .go.jp:政府系機関(例:厚生労働省)
病院に行くかどうか迷った時の判断基準
子どもが実際に発熱しているとき、すぐに病院に連れて行くべきか、様子を見るべきか迷うことがありますよね。
そんなときは、症状を確認し、判断チャートを活用するのが有効です。リンクは上部の「今すぐ判断したい方へ」に掲載しています。
また、小児救急電話相談(#8000)を利用すれば、医師や看護師が対応してくれるので安心です。
信頼できるサイト、便利なサイトの例
- こどもの救急(日本小児科学会)
- 東京都立中央図書館「健康・医療情報の調べ方」
- MSDマニュアル家庭版
- KOMPAS(慶應義塾大学 医療・健康情報サイト)
- MEDLEY(医師たちが作るオンライン医療事典)
よくある質問
Q.子どもが熱を出したけど、元気そうな場合でも病院に行くべきですか?
A.元気に食事や水分が取れていれば、様子見でも大丈夫なことが多いです。不安があるときは#8000に相談しましょう。
Q.インターネットで病気を調べると、重い病気ばかり出てきて不安になります
A.検索結果には重い病名が出やすい傾向があります。公的機関や大学病院など、信頼できる情報源を選ぶのが安心です。
Q.「こどもの救急」は何歳まで使えますか?
A.原則6歳までですが、判断の目安としては年齢を超えても参考になる部分もあります。
Q.GoogleとYahoo!、どちらで調べるのが良いですか?
A.医療分野では、Googleのほうが信頼性の高い情報を上位に表示する傾向があります。
Q.ブログやSNSの体験談って信じても大丈夫?
A.体験談は参考になりますが、医療情報としての正確性には限界があるため、あくまで補助的に利用しましょう。
最後に
医療情報は万能ではなく、あくまで判断の補助です。
情報を鵜呑みにせず、最終的には専門家の意見を仰ぐようにしましょう。備えとして知識を持つことが、冷静な判断につながります。